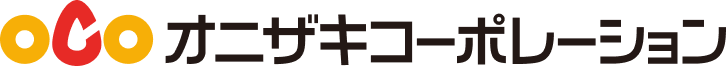オニザキについて
オニザキの創業は1956年(昭和31年)、法人化は1988年(昭和63年)、わずか半世紀の歴史です。もっと古参のごま業者はいくらでもあるはずです。それにもかかわらず、オニザキの歴史は、ごまの歴史です。こんなとんでもないことを申し上げるのには、理由があります。
今では想像もできませんが、ほんの40年ほど前までは、ごまは、「洗いごま」や「いりごま」として売られていて、各家庭で、すり鉢ですって使うものでした。そして、その少し前は、「洗いごま」もなく、ごまを量り売りで買って、自分でゴミを取り除いて、洗って... オニザキの創業は、そんな時代です。
オニザキは、「家庭ですぐに食べられる」ことを目標にして、「洗い(ゴミ取り)」や「焙煎」を専門に行なう「メーカー」です。そして、オニザキは、このメーカーの草分けです。今では、すぐに食べられる小袋入りの「すりごま」 がアタリマエになりましたが、これはオニザキが手さぐりで作り上げてきたもの。オニザキの歴史です。
すり鉢ですった「手作り」から、工場生産の「製品」へ。食文化として考えると、ちょっと寂しくもあります。しかし、米の例を考えてください。昔のように臼と杵を使って、家庭で精白することなど、現代では考えられません。無洗米まで売られ、伝統的な精白より、ずっと高いレベルの製品を利用できるようになりました。
現在のオニザキの製品は、すべて近代的な工場で生産されています。しかし、必ずしも量産できる製品ばかりではありません。製法は、家庭で作る「すりごま」とは異なりますが、それぞれの工程で、手作業を取り入れながら、最高の味と香りを追求しています。「家庭の味を超える」、これがオニザキのテーマです。

ごま屋のはじまり
現在では、「ゴマ」は小袋入り。そのまま使える状態で売られています。しかし、これは、数千年にも及ぶゴマ利用の長い歴史で考えると、ごく最近のことです。この物語は、今から50年ほど前、昭和30年代から始まります。この時代、店で売られているのは、産地から入荷したままのゴマ。さまざまなゴミや砂粒などが混じっています。食べるためには、それぞれの家庭で、ゴミを取り除き、煎って・・と手間をかける必要があります。オニザキの原点は、こんな時代のゴマの卸売り業者です。
佐賀市のとある雑穀問屋で働いていたお父さんは、ゴマの卸しの仕事をしていましたが、もともとあまり体が丈夫でなかったお父さんは、ある日、病気になってしまいました。一家の大黒柱が寝込んでしまい、途方にくれたのはお母さんです。三人の子供をかかえ、これから生活していかなければならなかったのです。
そこでお母さんは、このゴマを手で洗い、小さなごみを一つ一つ丁寧に手で取り除いて小売店へ卸す仕事を始めました。自宅で出来ることはそれしか思いつかなかったのです。洗ったゴマは日光にあてて充分に乾かします。天気の日には庭いっぱいに広げたござの上でごみを取り除くお母さんの姿が見えました。袋に詰めたゴマを自転車で配達し、帰ってくるとゴマを洗う。そんな毎日でした。
ごみの混ざっていないゴマは大変好評で、少しずつ注文が増えました。そのうち小売店から「いりごま」や「すりごま」の注文が入るようになり、お母さんの仕事は忙しくなっていきました。大きな中華鍋でゴマを煎ったり、すりばちでゴマをすったり、それまで家庭で行われていたことが、商品に求められはじめたのです。日本が豊かになろうとした時代です。

メーカーへの道
昭和40年代、高度経済成長とともに、スーパーマーケットがたくさんできました。忙しくなったのは、オニザキなどの卸売業者。スーパーマーケットでは、ゴマのはかり売りなど不可能。小袋入りの製品としなければ売れません。「洗いごま」、「いりごま」など、現在と変らない形態の「製品」が一気に流通するようになりました。
昭和43年のこと。お母さんの忙しさを見てきた息子は18歳。「商売はしたくない」と思うものの、とてもお母さん一人ではさばけない注文が入ってくるようになって、手伝わざるを得ません。晴れの日はゴマを洗い、お天気の悪い日と夜は、煎ったりすったり。親子2人で夜中まで仕事に追われました。
ある日のこと、1枚のパンフレットを目にしました。それは、ミキサーの広告です。息子は機械化を思いつきます。電話帳で機械メーカーを片っ端から調べ電話しました。一軒一軒に作業内容を説明し、機械化したい旨を伝えました。ゴマを作る機械などどこにもありませんでしたから、考えを伝えるのも一苦労でした。
やっと、あるメーカーが「それならできそうです」と言ってくれました。表は土砂降りですが、息子はいても立ってもいられず、「今から行きます」と電話を切りました。まだ見ぬ「すりごま製造機」を頭に描き、車に飛び乗ったのが、昭和46年でした。3ヵ月後、ゴマを加工する機械が納品されました。大きな釜にハンドルをつけたようなヘンテコな機械でした。
これで楽になる、と親子で喜びましたが、この機械は思うように働いてくれませんでした。均等に熱が伝わらなかったり、かき混ぜにムラができたりと、使い物にならなかったのです。その頃は、近所の人たちも手伝いにきてくれていましたが、夜中の1時、2時まで働く毎日が続いていました。そして、息子はどうしても、機械化を諦めることができず、模索を続けることになります。
「自分で機械を改良してみよう」息子はそう思いました。もともと整備士になりたかったのですから、機械いじりは好きだったのです。しかし、これは、長い道のりでした。

家庭の味を超える
ゴマをする工程も、試行錯誤の連続でした。すり鉢や回転臼では、パサパサした味になります。これらの道具であらびきにすると、粒を鋭く切った状態になるからです。回転臼は、粉末にまで砕く製粉の道具。すり鉢は、ネリゴマ作りには適していますが、粒の食感を残すあらびきには向いていなかったようです。
よりしっとりとした味に。
思いつく方法は、古くから使われている臼と杵。息子は、自宅の倉庫から餅つき用の杵と臼を取り出してきて、 早速試してみました。手作業でしばらく搗(つ)き続けると、しっとり感のあるゴマが出来上がりました。甘みもあります。 近所の人に食味いただくと、この搗いたゴマは、家庭で作るすりごまよりおいしいと、大変好評。あとは、この機械化でした。1971年(昭和46年)、「杵つき」の機械が完成しました。石臼の上で、動力を使って杵を上下させるだけの簡単な構造でしたが、ゴマ加工の機械としては、おそらく、日本で(世界で)初めてです。機械だけではありません。作り方も、従来の「ゴマをする」作り方から進化し、「杵つき」を取り入れた製法になりました。その後も究極のゴマを求め、杵の本数や先端の形状改良、重量の変化、臼の大きさや深さから材質にいたるまで、味と香りの歴史は、テストと改良の積み重ねです。
日本が第二次ベビーブームの頃から始まった「ごま」の工業化ですが、オニザキの歴史はゴマの現代史。今では元祖!「家庭の味を超える」、「すぐに食べられる小袋入りのゴマ」として評判です。
杵つき
臼と杵は、米などの穀類を精白する道具として使われていました。粒の外側から、少しずつ崩しますから、玄米の外側のヌカを削るのに好都合だったのです。臼と杵は家庭の必需品で、日常の道具でした。しかし、昭和30年台、オニザキ創業の頃になると、米の精白は小売店(米屋さん)の仕事。臼と杵は、餅つきなどの非日常を演出する小道具となって、一般家庭では、あまり見られなくなっていました。臼と杵を使って、ゴマをつぶすと、外側の硬い皮を細かく粉砕できるので、好都合。これは、誰でも思いつきます。しかし、家庭で使うゴマは、臼と杵でつぶすほどの量ではありません。どうしても、すり鉢によらざるを得ません。
臼と杵という伝統的な道具を使って、可能な限り手作業で仕上げた工場生産。これが、家庭の味を超えます。
つきごまの元祖として
1971年(昭和46年)の「杵つき機械」完成から39年が経った2010年5月、オニザキは、一つの大きな決断をいたしました。商品名を馴染みのある『すりごま』から『つきごま』へ変更したのです。「すり鉢ですったゴマ」を『すりごま』と呼びますが、オニザキ独自の製法である「杵と臼で搗(つ)いたゴマ」を『すりごま』と呼ぶには少々ムリがあります。また「すり鉢ですったゴマ」と「杵で搗いたゴマ」とでは、見た目のしっとり感や風味、食感にいたるまで大きく異なるため『すりごま』というカテゴリーには大きな違和感を感じていました。『すりごま』の多くは、油分の滲み出しが少なく、見た目にもパサついた感があり、『つきごま』と比べると風味や食感などで劣ります。逆に『つきごま』はゴマの粒を杵でつくことで、ゴマの油分や旨み成分が適度に滲み出し風味や食感に優れています。
これら品質上の違いを明確にするため、また、多くの「すりごま」製品よりもひと味違う「おいしいゴマ」として、2010年、製法に忠実な名称『つきごま』への変更に至りました。これまでの「おいしいゴマの元祖」としての立場はもちろん、「すりごま」「いりごま」「ねりごま」の3大カテゴリに加え、今後は『つきごま』という新カテゴリーの元祖として、普及に努めていくこと、これが、これからのオニザキの使命です。